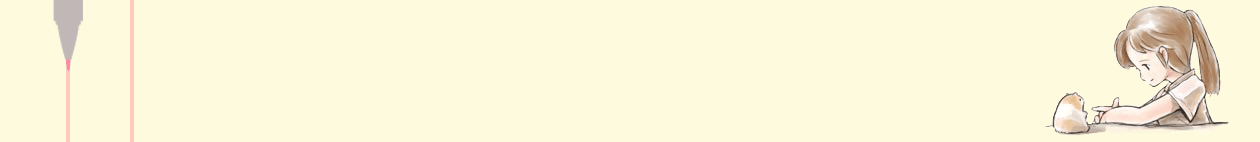ドイツは朝が早い。パン屋さんが朝の6時から開いていたり、ごみ清掃車が朝8時ごろどっかんどっかん回収に来たり・・・はたまた郵便屋さんが8時ごろすまして速達を持ってくる。
寝るのが趣味(←ものぐさ?)な私には、とーってもキツイわけです。
我が家は昨日から工事中。長年気に入らなかったカーペット敷きの玄関と廊下(これがむやみに長い。動く歩道をつけたいほどである)を板張りにすることにしたのだ。フローリングというやつである。
その初日である昨日。朝早く来る可能性もあるから、8時にはスタンバイできているようにと、Dとともに7時過ぎに起きることを決意。すると・・・
ビィィィィィイ!
と玄関のベルが鳴った。(我が家の玄関ベルは、恐ろしいほど轟音が鳴る)その時の私たち二人はというと・・・
爆睡中 (@_@;)
時間は7時ジャスト。この時の私とDのリアクションは、それぞれの性格を表すものであった。
Dは飛び起き、とりあえず寝グセになった頭を手でなでつつ、混乱してベットのそばをくるくる回っていた。で、私はというと、ベットからぴくりとも動かず
あのさぁ、早すぎだよ早すぎ・・
とぶぅたれていた。(-.-)
で、私たちはどうしたかというと・・
あのぅ、すみませんがあと30分後にもう一度いらしてください。早すぎです
と、追い返した。<(`^´)>エッヘン ←いいのか・・・?
まぁ、Dの寝グセをみた彼らは、我々がしっかり寝ていたことが100%わかったらしく、おとなしく30分後にまた来てくれた。いい人だ♪
昨日も帰り際、
明日7時に来るから♪
というので、
いえ、7時半でお願いします。と切り返しておいた。
その結果、今朝は7時45分ごろ
君たちのために、すこし遅めに来てあげたよぉ♪
と、ゆっくりめに現れた。うん、本当に良い人たちだ。
それでも今朝からは6時45分起き。これが2週間続く。うぅ、つらい・・。
私のサイトFromBerlinへは
こちらからhttp://www.rikakomurata.com
個性?
飛行機などで<予約番号>というものを受け取ることがある。アルファベットと数字で組み合わされた LPE5J2 のようなもの。電話でこの番号を教えてもらうとき、聞き間違いを避けるために それぞれのアルファベットに言葉をつけて言われることがある。
私がこれまで経験した中では、
パリのP ロンドンのL
などのように、地名をつけるもの、あるいは ステファンのS、ボブのBなど人の名前をつけるもの、この2つのいずれかだ。ピアノ協奏曲の楽譜にも、A,B,Cなどのアルファベットが書いてあることが多い。オーケストラとのあわせの時、ここから弾きましょう、などと大人数に指示する場合に便利なのだが、これもドイツでは、ハインリッヒのHから始めましょう、などと呼んでいる。そういう経験から、多少の違いはあっても、大体の場合は共通で、Lはロンドン、Pはパリなどとわかりやすく統一されているんだろうと思っていた。
先日ある日本の航空会社(ヨーロッパ支店)との電話のやり取りで予約番号をいただく際も、そんなわけで心の準備は整っていた。電話口は日本人女性。
女性:お客様の予約番号は、ロンドンのL・・・
私:(お・・・ロンドンね)
女性:シュガーのS
私:( ̄△ ̄;)エッ・・? シュガーー? 砂糖っすか・・汗
女性:数字の5、
女性:パパのP
私:(゜∇゜ ;)エッ!? パ・・・パパ??
いやぁ・・・おかげさまで驚いてしまい、番号を聞き取るどころではなく、
シュガー?パパ??
と頭の中に巡ってしまい、2-3度聞き返す羽目になってしまった。
もちろん、もう一度繰り返してくださる際も、
シュガーのS、 パパのP・・・であった。なんだか和むなぁ・・・・
私のサイト FROM BERLINへは
こちらからhttp://www.rikakomurata.com
そして また・・・走るパパ
先日、D+パパ+私という3人で、地元の小規模ショッピングセンターに行った。
車を最上階に止め、ショッピングセンターにも最上階から入り、父は一階にある銀行に用事をしにいき、その間私とDは最上階で買い物をするという予定であった。
パパ:じゃ、パパは一階に行って用事を済ませるから、
またあとでね!(。・_・。)ノ
と、父だけがエスカレーターで降りて行った・・・・
・・・・・・・はずだった・・・・・・・
ふと、視線をエスカレーターに戻すと、なーんと下に降りて行くエスカレーターの真ん中あたりを父が逆走してくるではないか。
ε=ε=ε=ε=ε=┏(゜ロ゜;)┛ダダダッ!!
反対に進むエスカレーターに負けじと足をフル回転。どうも上にのぼってこようとしているらしいが、進む気配なし。同じ場所で走り続けるハムスターのようであった。
あ・ぜ・ん (・_・;)
とした私たち。
私:パパ、どうしたの?
パパ:通帳忘れた・・ゼェゼェ (相変わらず走り中)
私:それなら、1度下の階に降りてエスカレーターで戻っておいでよ。
というと
パパ:あ、そうか (・o・)
とくるりと向きを買え、すーーっとエスカレーターを降りていったのであった。
なんともいえない父の背中よ・・
私:あのさぁ、逆行せずに下に降りてまた上ってくるということは
考えなかったわけ?(  ̄_ ̄)
と聞くと
パパ:必死で走ってたからなぁ。
でもさ、エスカレータより早く走れてたぞ♪(⌒~⌒)ニンマリ
となんだか満足げ。いやぁ・・・進んでない様に見えましたが・・・(- -;)
私のサイトFromBERLINへは
こちらからhttp://www.rikakomurata.com
一本のおしるこ
先日Dと日本で電車に乗っていた時のこと。その電車は、指定席などがあるわけでもない、いわゆる普通の電車。各車両の左右に長い椅子があり、みんな横に並んで座る形式。その電車の始発駅から、私たちは乗車した。
出発までまだ5-6分ある。空いている席を探し、私たちは車両から車両を移動。数席あいている椅子をみつけ座ろうとしたところ、一番手前端の席に缶ジュースらしきものが置いてある。端っこの席に座りたかった私たちは、反射的にそれを足元に置き、座ったのだが、ふと、頭に不安がよぎった。
私:ねえ、誰かがこの席取ってるんじゃない? 始発だし。
D:えーー、こんなもので取っておくかなぁ?? (・。・)
こんなもの・・・・。そう、缶ジュースと思われたものは、よく見ると
<おしるこ>だった。しかもまだ温かい。
じゃあ、出発まで待ってみよう。(^。^)
そして私たちは、席をひとつ横にずれ、Dが先ほどのおしるこの缶を端の席に置いた。
なにを思ったか、Dは缶を立てて置いたため、その席は
おしるこ様
が着席しているようになった。
ふと、
ねえ、これ危険なものだったりして・・・
という不安も一瞬よぎったわけだが、
ま、いいか♪ (←いいのか?)
と楽天家の私たちは、(動くのが面倒くさかったという説もある・・)結局そこから動かず。
発車ベルが鳴る。他の席はどんどん埋まってくる。残り少ない空いた席を探し車両から車両を渡り歩く人の量も増え、私たちの目の前を左から右から通って行く。
遠くからだと、空いているように見える私たちの隣をめざして、猛スピードで歩いてくる人たち。みんな、横目でちらりと狙う席を定め、クールを装いながらも、かなりの早足で迫ってくる。でも、席に鎮座したおしるこを横目でちらっと見たとたん、どの人も少し恥ずかしそうに、すーっと通り過ぎて行くのだ。なんだかおかしくなって、笑いそうになってしまった。
誰が私たちがしたように、缶を下ろして、座るかねぇ・・・
とDと観察することしばし。電車が出発してからも、その席は相変わらずおしるこ様のものとなっていた。高校生の女の子は、座ろうと思って足を止めたら、おしるこ様と向き合ってしまい、思わず
“おっ”
と短く一声あげ、やっぱり動かそうとはせず、去って行ってしまった。
みんなの反応がなんとも面白い。
電車はすでに発車し、もう誰もその席を取っていないのは明らかなのに、缶を動かして座ろうとする人は誰もいない。結局私たちが下りる頃は、電車はかなりの人で込んでいたにもかかわらず、その席だけは、依然おしるこが鎮座していた。
こんなこと、フランスじゃ考えられない・・・
と、Dがつぶやいた。そしてニヤッと一言。
これから、日本で隣の席に誰も座らせない方法を学んだぞ。
おしるこ、買おっと♪ (^v^)
私:いや、違うでしょ・・・ (-.-)
私のサイトFrom BERLINは
こちらからhttp://www.rikakomurata.com
学生という日々
学生の時、毎日の学校生活に追われ、あまり考える余裕がなかった。
今、半人前ながら社会人となって、学生時代の宝の山だった有難い日々を痛感している。
私がベルリン芸大の学生だった時代、クラスで定期的に弾き合い会があった。毎回朝の10時、時には9時から始まり、夜の19時すぎまで・・・お昼休み1時間ぐらいを除いては、本当に1日中かかる勉強会だった。
クラスが集まり、演奏したい者が弾き、みんなでその演奏をどうすればもっと磨けるか、頭を悩ませ意見を交わし合う。面白くまた大切だったことは、先生が“こうだ”と教えるのではなく、生徒がみんなで意見を交換するということ。先生は必要があれば、言葉をはさむが、決して“答え”を述べるわけでもなんでもない。みんなで考える、という機会だ。決して人と比べるためではなく、もし今の演奏が自分だったら、どのようにこれを磨くべく練習していけばよいか、ということをいろんな意見を通して様々な角度から考えさせてもらえる貴重な機会だった。なるほど、そんな考え方もあるんだと気付かされたり、自分の意見を言おうと思っても、うまく説明できず、自分のあいまいさを痛感させられることもあった。何となくこうかな、とは思っても、実際言葉でそれを説明するということは非常に難しかった。あいまいでなく、明確な理解が必要とされるからだ。知らない曲もたくさん聴くことができ、新たな発見がたくさんあった。あの楽器から、こんな色も出るんだ・・と、色の可能性をさらに増やせる機会でもあった。頭も、耳も、心も・・・一度にたくさん勉強できた。
そして、レッスンをするようになった今、あの時の経験がどんなに役に立っていることか。
一生懸命ひたすらピアノの前で練習し、レッスンを受け、直してもらって帰る。これでは、卒業後は何も残らない。自分で理解し、消化し、活用していくためには、受け身ではどうしようもない。自発性、積極性そしてエネルギーが何よりも大切だ。
そして自分の練習だけにこもらず、仲間の演奏を聴いたり、仲間と話して栄養をもらったり・・・決して誰かと比べる為ではなく、栄養をたくさん吸収するために、そして自分の考えを方を豊かにするために仲間とともに勉強をする。いろんな人に、いろんな音に、いろんな考え方に触れてこそ、自分というものが熟成されていく。プロの演奏だけでなく、同じ世代の仲間の音楽、考え方に触れる・・・そんな貴重な機会の様に、学生だからこそできる、いや、学生の間しか充分に時間をとることができないことがたくさんある。
今しかない大切な時間。今しかできないことを、積極的にどんどん試みてほしい。決して間違いを恐れずに。
私のサイトFromBerlinへは
こちらからhttp://www.rikakomurata.com
またまた パパ 水戸黄門? の巻き
さすがパパ。ぼけ度が違う。脱帽です。
先日のパパからのEmail:
============
今日はすごく天気が良かったなぁ。
洗濯物も河合太郎!
============
ん?(゜.゜)
と読んだ瞬間 私の頭には、???マークが飛んだ。
おわかりでしょうが、
乾いただろう!
の変換ミスです。ハイ。わざとぼけようと思ってもここまでぼけられん。
あの人は天然だからなおさらすごい。
ここまで、河合太郎! って言いきられると、
この紋所が目に入らぬか!
の勢いである。
私のサイト FromBERLINへは
こちらからhttp://www.rikakomurata.com
うちのパパ “誰それ?”(-“-) の巻き
時々ひょうきんなうちのパパ。またやってくれました。
先日、“ゆかり”という名前のおいしいえびせんべいを買ってきてもらいたく、
パパにお願いしていた。
パパ:お、“ゆかり”ね。了解了解。それはどこの会社が出してるお菓子?
私:○○会社だよ、デパートに行ったらあるからよろしくね!
と会話を終え数日がたったある日、パパよりメールが入った。
パパメール:
おう!この間の“さゆり”買ったぞー
私:(-.-)
“さゆり”とご丁寧に“ ”で囲んでいて、えらく自慢げなのだが、
あのぅ、
さゆりって・・・、いったい誰じゃぁ(――〆)
結局、正しいものを買っていたのだが、なぜか数日の間にパパの頭の中で
“ゆかり”が“さゆり”になっていたらしい。
お店の人に、“さゆり”ください・・・って言わなくて良かった。ほっ(+o+)
私のサイトFROM BERLINへは
こちらからhttp://www.rikakomurata.com