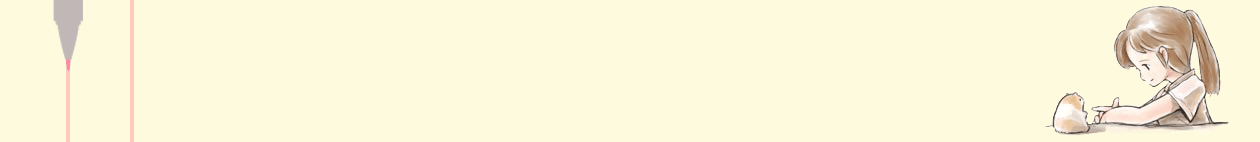パリから愛をこめて♪
素敵なクリスマスをお過ごしくださいね

ただ今のベルリンは・・・
マイナス14度
でございます。
((((~~▽~~ ;)))ブルブルブル
何よりも、乾燥がすごい。手足も唇もバリバリになるうえ、
ピアノを弾くので指先が指紋のところからぱっくりと開いて
それはそれは痛い・・・。
思い出すなぁ、私が留学始めた年。96年。あの時はマイナス20度以下になっていた。
今年も来るのだろうか・・・。
されど さゆり・・・
以前の“さゆり”事件以来(2009年1月15日の記事参照)、私はさんざんパパをからかっていた。そうこうして数カ月たったある日、再びゆかりをいただく機会があった。すると、パパが
‐あのな、この“ゆかり”というお菓子の名前はな、人と人との結びつき、という意味があると思うんだ。ほら縁もゆかりも・・・とか使うだろう。
と、えらく真面目にのたもうた。ゆかりをくれたHちゃんと二人で顔を見合わせ、私が
私:またぁ、適当なこと言って・・・。前は《さゆり》とか言ってたくせに。
と苦笑して、ふとその缶を見てみると、なぁんとゆかりというひらがなの後ろにうっすらと“縁”という漢字が浮き立っているではありませんか。思わぬ知った父の雑学に、
ほぉ (゜o゜)
とすっかり感心して、
私:おぉ、パパすごいじゃん。面目躍如だね!!ヽ(`▽´)/
と、褒めちぎっていた。そう、それは半年以上前のこと・・・。
===========
そして時は過ぎ、秋も深まるつい先日、久々に私が注文しておいた“ゆかり”が何箱か届いた。受け取った父がひとこと・・:
パパ:おーい、さゆり 届いたぞぉ (゜o゜)
私:(-.-) ゆかり・・・ね。
彼は何も学んでいなかったらしい・・・。
私のサイトFromBerlinは
こちらからhttp://www.rikakomurata.com
せんくら終了!
いやぁ、楽しかった。朝ホテルを出たら夜まで戻らないという二日間びっちりと詰まった予定。3日で101個の演奏会という、大きな音楽祭。でも、オーガニゼーションの素晴らしいこと。見えないところで本当に多くの方が戦場のように忙しく働いているのだろうが、どの人もいつも笑顔を絶やさず、適切に接してくれる。おかげさまでこちらも、自分のリズムを良い具合に保つ事ができ、できることなら全員にお礼を伝えたかった。
50人以上の演奏家がいるにもかかわらず、意外にも舞台裏では全くすれ違わない。ほぼ誰にも会えず・・。唯一話せたのが、ヴァイオリンの西江辰郎さん。王子と呼ばれているとかで、女の子に大人気。へへ、へへと笑う、とてもさわやかで素晴らしい方だった。
楽屋裏には、飲み物を用意してくれているスペースがある。そこでコーヒーをついでいたら、ピアノの若林顕さんがいらした。あ、本物も写真とそっくりだ、などミーハーなことを考えつつ“お疲れ様です”と声をかけ、彼もさわやかに、どうもと言って通り過ぎた。
しかーし、これで終わらないのが私の人生。
そこへ若林さんが戻って来て、
若:あのぉ、すみませんが楽屋4番はどこですか?
私:いやぁ、ちょっと私にはわかりません・・・・ (-.-)
そう、まぎれもなくスタッフと間違えて声をかけられ、アーティストと書かれたバッジを下げているにもかかわらず、スタッフと思いこまれたままこのフェスティヴァル終了したのでした。汗
そんな感じで、いろいろな演奏家が集まっているにもかかわらず、どなたとも話す機会がなかったのが少し心残り。でも、全員の演奏家が私たち同様、びっちりと詰まったスケジュールで動いているだろうから仕方ない。
演奏会では、お客さんの集中力に驚かされた4公演だった。マイクで“こんにちは”と声をかければ、大きな声で全員が“こんにちはー!”と返事をしてくれる温かさあり、でも私たちの4つすべての公演で、演奏が始まると息をのむような静けさを作り出してくれた。本当にすばらしいお客さんだった。おかげさまでこちらも良い緊張を保つ事が出来、心から楽しんで演奏させてもらった。演奏後のサイン会でも、温かい声をかけてくださる方の多いこと。なんだか私たちの方が、お客さんからエネルギーをもらった感じがした。
みなさん、どうも有り難うございました・・・。(^-^)
明日から録音。がんばるぞー。
ぐぇ・・・
前回のブログ以来、今もってまだフランスの山の上で過ごしている。真冬日からスタートしたものの、その後30度近くなり真夏日になったり、雷雨になったり、うっすら雪が見えたり・・・山の天気は本当に変わりやすい。それにしてもアルプスの壮大な山は一言では表現しきれない。心をリフレッシュできる最高の機会に感謝の毎日である。
ところでこの山の上で、この夏は5回演奏させてもらう機会をいただき、これまで4回が無事終了した。まぁ、物心ついた時から驚くほど緊張するタイプである私は、毎回本番前の数日あるいは数時間、まさに≪全身で≫緊張している。前回のコンサートでは、昼寝中に緊張でほぼ金縛りのようになり、手足がしびれるわ、昨日は舞台上で途中でなんと足が震え出し、あまりにがたがたがたがたなるのでペダルが思ったように変えづらいわ、毎回の本番がスリル満点である。
ちなみにこのホールの特徴は・・・
ハエが飛んでいる
ことである。舞台上でハエがぶんぶん飛んでいて、どうやら最後の力を絞っているらしく、時々脱落したハエたちが落ちてくる。落ちてくるのは結構だが、最後の力を振り絞っているため落ちた後はほぼ動かない。
で、ご存知の通り、珍体験ばかりで私の人生がいろどられているので、このハエも、もちろん逃すわけがない。そう・・・それは去年の演奏会中の出来事である。
ぽたっ
と、ハエが鍵盤の上に舞い降りた。というか、落ちた。ぴくぴく・・ともせずほぼ動かない。お陀仏のようである。
で、私はというと・・・
演奏中・・・(@_@;)
お願いだから、その鍵盤を弾かずにすみますように・・・・
と祈りながら、与えられた曲を弾き進めているのだが、
あるとき・・・・その時がついに来てしまいました。
ムギュ (・.・;)
ええ、ええ・・・ご想像にお任せいたします。
しかーし、その時の小指の感覚と言ったら一年たった今でもしっかり覚えている、というか忘れられない。
何もなかったかのように無表情で演奏し続けた私に、我ながら拍手!!であります。
^(ノ゜―゜)ノ☆パチパチ☆ヾ(゜―゜ヾ)^
今年はこれまで4回、譜面台やピアノの中に墜落するものはあるが、演奏中の鍵盤はまだ無事である。あと一回の演奏会、たのむぞハエさん・・・。
さ・・・・
寒いっ!!!!
今、仕事でフランスのクールシュヴェールという町に来ています。
ここは標高1850メートル。山の天気とあって変わりやすいのだけど、
今日は何と、今(夜中23時45分です)の時点でマイナス3度・・。
ここは南半球か??って感じです。夏はどこへ・・???
まさに凍っております。
泊っているホテルは、がんがんに暖房がきいていて
山頂のほうは白く雪がかかっており、今何月だか分らなくなりそう。
そんな冬山から中継でした。笑