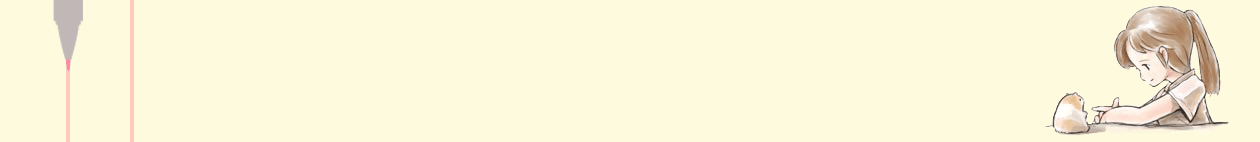-こんな時勢に、音楽なんかやっていていいのだろうか
-こんな時に、音楽で何ができるか
という言葉を震災後よく耳にする。
でも、<音楽で何が出来るか>・・・そういう方向で考えていたら、余計分からなくなるのではないかと私は思う。それを教えてくれたのが、先日のベルリン芸大でのチャリティーコンサートだった。日本人留学生が発起人となり、種をまいてくれたチャリティーコンサートが、学校主催の大規模なものとなった。私とDも、そこで演奏をさせていただくという光栄な機会をいただいた。短い期間で若い日本人や学校関係者が文字通り“必死の”準備をしてくれ、迎えた当日。学校に足を踏み入れて、言葉を失った。
1996年から15年のベルリン生活で、あのホールで1度も見たことのない数の人、人、人・・・。更には、満席だからと門前払いを受けた聴衆が舞台裏に列をなした。開演ぎりぎりに、舞台席も急遽用意された。会場は1200人ほど入るはず。舞台上の聴衆を合わせれば1400人ぐらいになったであろう。
ここはドイツ。コンサートの趣旨は日本。
日本のために、ドイツ人がこんなに・・・・いや、違う。もうそこには国籍もなにもなく、ひとりの<人間>としてなんとかしたい、と思う魂がホールに集まったのだ。
チャリティーコンサートとは、音楽を通してお客さんに何かを伝える・・・そして賛同していただいた方に募金をいただく、そんな考えをしていた自分が恥ずかしくなった。あふれんばかりの人から、そのまなざしから、舞台に立つ私のほうが、はっと気がつかされた。心に感動を与え、エネルギーを注ぎ込み、しっかりと前を見据える力をもらったのは、私のほうだった。どんな言葉をかわさずとも、足を運んでくれ、私こそ私こそと力を貸してくれようとするそのまなざしから、心が激しく突き動かされ、揺さぶられた。
どんな言葉も、必要ない。音楽を演奏する者があり、聴く者がある。主役はいない。いや、むしろ全員が主役だった。その誰もが、音楽を耳にしながら、それぞれの思いでその時間を分かち合い、それぞれの心に思い思いの感動や衝撃、栄養をたっぷり吸収し、帰っていく。そんな場だった。
自分が音楽を共にすることの意味を見失いかけていたとしたら、このことだけ刻み込んでいて欲しい。
音楽は、生活には不可欠ではないかもしれない。でも
音楽は、人間に必要なもの・・・
だと。
私のサイトFromBerlinへは
こちらからhttp://www.rikakomurata.com
moru のすべての投稿
心
折り鶴を折った。

ここベルリンでも、本当にたくさんのチャリティー活動が行われはじめている。
その一つ、ベルリン・フィルからの要望で、チャリティーコンサートにいらしてくださるかたに鶴を配りたいということで、至急大量に必要なため、ベルリンにいる日本人に鶴を折ってくださいというインターネットでの呼びかけがあった。
2400羽必要で、前日までに1200しか完成していないとの記事に、私も朝から50羽急いで折って届けた。鶴を折るというのは、日本人にとって当たり前というほど皆ができることだけど、あらためて折ってみると、その工程はけっこうややこしい。
Dが手伝おうと思っても、難しすぎるようだった。
ふと、折り紙って日本の伝統なんだなぁと・・あらためて感じたりした。
4月に、ベルリン芸大でもチャリティーコンサートが行われようとしている。
日本人留学生数名が、地震直後に立ち上がり、チャリティーコンサートを!と奮闘している姿に、学校が協力を申し出てくれたようで、学校主催のコンサートが開かれるまでに発展したらしい。
日本人留学生の積極的で、熱のこもった訴えとその行動力に、なんとも言えない温かい気持ちと、こんな若者がここベルリンにいるのだという嬉しさで満たされた。
私とDも演奏させていただくことになっている。
どんな言葉でも十分に表せない、今の私の心に渦巻く気持ちを音にのせたいと願っている。
あたり前の平凡な日々、あたりまえの笑顔・・・一瞬にして、それがどれほどの宝物であったかを知らされ、今更それを再認識する自分を恥ずかしく思ったりもする。
国を超えて、国籍を超えて、本当に多くの人達が心を痛めている。それをここベルリンでも強烈に感じる。
今必要なことは、おそらく団結することだと思う。心を1つにして、今できることをこなしていく。
こんな残酷なことがどうして起きなければいけないんだろう。
さすが芸術の街? (2)モスクワ2010 公演①
そんな恐ろしい思い出とは裏腹に、今回の旅はDの晴れ舞台を芸術の本場、モスクワで聴くと言う何とも楽しみなもの。
古くからある伝統の チャイコフスキーホールがその会場だった。2夜連続の演奏会で、初日はオーケストラとサンサーンスの協奏曲4番、そして翌日はソロリサイタルであった。ホールはこんな感じ。(写真をクリックすると拡大されます!)

まず協奏曲の日。19時の開演というので18時50分ぐらいに私は着席。ぎりぎりにホール入りしたと思ったのに、1700人近く入るホールは、開始10分前にもかかわらず、まばらな聴衆しかいない。
そして19時。開演時間のベル。ベルは既に15分前ぐらいから鳴り始め、これでもう3度目である。すると、そこからぞろぞろ、ぞろぞろっとお客さんがホールへ入り始める。
みなさん、開演時間ですよねぇ、既に・・・・。(・ε・)/
ぎりぎりまでワインなどを楽しんでいたのだろうか。みなぜーんぜん急ぐ様子もなく、席へ。そしていつのまにか、その1700席が満席となったのである。皆が客席してホールの明かりが落とされたのは19時15分だった。
モスクワ人は半端無くマイペースである。
あとでDに聞いたところ、最近のロシアでは当たり前に15-20分遅れで演奏会が始まるとか・・・。驚いた。
やっと始まると思ったら、何やらアナウンス。ロシア語なのでなんとなく想像できる言葉だけをかいつまんでみたところ、こんな進行だった・・・
と思う。(^_^;)
-今日はフランス音楽をテーマとした演奏会です、という紹介。
-フランス大使館などからの招待客への御礼と、紹介。
-今日のソリストの紹介。
-今日の指揮者の紹介。
-プログラムを一曲ずつすべてアナウンス
つまり・・アナウンスが長い・・・。とても長い。(`□´)
そして、やっと1曲目のアナウンス。たった今、全曲紹介したばかりなのに。
アナウンス:ではフランクの交響曲です。指揮者はマエストロ、OXOXOXOXです!!
と流れ、拍手が起こる。一度拍手が鳴りやみ、舞台右手にあるカーテンに皆が注目。そして、それが かなり勢いよく、
サッ!!
と開いた。どうみても、カーテンの後ろに人が控えていて、その人がくす玉をひっぱるように、思いっきりカーテンを開いた、という”手動感“にあふれていた。
たとえるなら、紙芝居のはじまりのような感じである。
そしてマエストロOXOXOXOXが登場。演奏が始まった。前半がシンフォニーというプログラムで、そのまま休憩へ。次はDの出番である。どきどき。
ホールの明かりが落ちたと思ったら、またアナウンス・・・・。
-曲目は、サンサーンスピアノ協奏曲第4番です!(さっき言ったよねぇ)
-ピアニストはフランス人、Pascal DEVOYON! (ってかさっき聞いた)
-指揮者は、マエストロ OXOXOXOX!!!! (だから、さっき・・・怒)
そして拍手。それが一度止まり、カーテンへ注目。紙芝居カーテンが
サッ!!とあく。
同じである。(-_-メ)
こことでふと気がついた。舞台の中央にあるパイプオルガン、舞台左の壁、右の壁、それぞれにうっすらと違う色の光が当ててある。薄い紫、薄い青、薄い赤であろうか・・・
フランス音楽、ということで演出をしていると思われる。舞台に色つきの光なんて・・・どこかのバーのようである。その模様は一番下の写真でどうぞ♪
コンチェルトも大成功!お客さんは、最後の音が終わる前に既に手拍子での拍手。気が早い!笑 あこがれのモスクワでのDの舞台ともあり、想像を絶するであろう彼の緊張を考えると、なんだか感無量だった。
そして最後は、デュカスの魔法使いの弟子。これは2台ピアノで私たちもCD録音していることもあり、非常に楽しみ。
いうまでもなく、アナウンス。
―次はデュカスの・・・
-指揮者は マエストロ OXOXOXOXO!!!
っていうか、1つの演奏会で、指揮者は変わらないでしょうが・・。(+o+)
ここでマエストロの名前が代わっていたら、こっちも驚くが、もちろん同じである。なんで毎回そこまで気合を入れて マエストロOXOXOXOXOXをアナウンス必要があるのだろうか。Dによると、古い伝統らしいが。(`-´メ) プンッ
演奏はこれまたすばらしく、それに加えてデュカスという作曲家の素晴らしい才能に改めて感動した。映像が浮かぶようなこの作品のすばらしさだけでなく、それを二台ピアノに書き換えてもオーケストラの世界がまったく失われていないのだと心から感じ、彼の編曲への才能へもあらためて敬服した。
すばらしい“紙芝居”演奏会だった。←(;`O´)oコラ
演奏会の模様 (照明が・・・カラフル・・・汗)
写真をクリックすると拡大されます



(次号に続く)
私のサイト、FromBerlinへは
こちらからhttp://www.rikakomurata.com
クラシックの街、モスクワ?? 1)2002年の思い出
クラシックの街、モスクワ?? 1)2002年の思い出
Dが、彼のチャイコフスキーコンクール受賞以来となる、大規模なロシア全国演奏会ツアーを開催していただいた。そう、このブログで無残な登場をしているDの本業は一応ピアノ弾きである。ロシア8か所をまわり、最後はモスクワでの公演。私はその最終2公演を聴きに、モスクワに合流した。
私が行くのは、2002年以来。その時は知人のコンクールの伴奏で同行した。
その年の思い出はというと、“大変”だった。ちょうどサッカーの世界選手権の真っ最中で、私たちが滞在しているときに何と、日本―ロシア戦が行われたのだ。ホテルそばの広場には、何千ともいう観衆が集まってモニターで野外観戦をする大盛り上がり。私たちはホテルにいた。
試合が進み、何と日本が勝っていると言うではないか。ホテルの窓から乗り出し、すぐ近くで盛り上がっている広場をみながら、イエーイ、日本万歳ヽ(`▽´)/ などと盛り上がっていたのだが、何か様子がおかしい。試合終了数分前になったら、その群集がなんだかこちらの方へ走って来るような・・・・と思っている間に、来たー!!走って来る大群。
かなりものもです・・何百人という大群が押し寄せる迫力は。(・・;)
そして、ホテル真下の通りに駐車してある車のうち何台かの車の上に人が飛び乗り、
ぼこぼこにしたと思ったら、群衆によって 裏返しに!!!車がフライ返し(違)・・・裏返し・・・ですよ!
つまり、そう。暴動化ってやつです。
そして被害を受けている車はすべて日本車。これは見てる場合じゃない。日本車どころか日本人も危ないではないか。というわけであわてて窓を閉め、カーテンも閉めた隙間から、外の様子を見続けた。するとひっくり返った車に火が放たれ・・もうただ事ではない。笑っていられなくなり部屋でぶるぶるぶるぶる・・・。
しばらくすると、部屋の電話が鳴った。コンクール事務局からだ。
事務局:日本人の参加者は外に出ないように。
(・。・; え・・?
やばくないですか、これ!
再び外を見ると、相変わらずの暴動、そして人が一人倒れている。それから間もなく、機動隊の大きなワゴンが数代到着し、ドラマで見るような防護服と盾をもった完全装備の機動隊が下りてきた。
ひょえー。ロシアの血はすごい。あばれるときは、とことん・・・である。
そんな中、知人の一人が、コンクールから割り当てられた練習時間となった。
知人:おれ、練習行ってくるわ
と、日本人外出禁止令にもかかわらず、出かけると言う。でも大切なコンクール。練習時間をこんな事で無駄にしたくないという気持ちもわかる。心配ながらも彼は、出かけた。
と思ったら、数分で帰って来た。(-_-メ)
知人:顔、蹴られた。((+_+))
ホテルを出たとたん、顔をとび蹴りされたとか。
翌日のニュースで、日本車はおろか日本食レストランも襲撃をうけ、我々のホテルの一回の窓ガラスもついでにめちゃめちゃに割られ、そして道路で倒れていた人は、暴動の最中に刺され、亡くなったという。
お・そ・ろ・し・い
これが、私の持った2002年のモスクワの印象でした。
(続く)
私のサイトFromBerlinへは
こちらからhttp://www.rikakomurata.com
今日のつぶやき
本当に素晴らしい人間ほど、なんて
謙虚なんだろう・・・・。
あけましておめでとうございます!
2011年がベルリンでも始まりました!
今年も、今という瞬間を楽しんで過ごしたいな。
今年もよろしくお願いします!
雪のベルリンより・・・

つかの間の夢・・・
つかの間の夢・・・
我ながら、ロマンチックなタイトルである。しかし、私のブログに限ってそんなわけなし。(=`^´=)エッヘン
2007年の3月に、ドイツで耳鼻科に行った話を書いた。まずはそれをご覧下され。
(開いたサイトの下の方の、2007年3/13の記事をどうぞ。)
http://www.rikakomurata.com/blog/2007/03/
そう、あれは3年前。冬空の空気に、のどをやられてしまい近くの耳鼻科に行った時。インターネットで、信頼できそうな顔の若いドイツ人先生の写真がのっていた耳鼻科に行ったところ、実際に出てきたのは半魚人だったという話である。(←いいのか、こんな要約で)
今、極寒の冬を迎えているベルリンで、またも先日のどをやられてしまった。4日ぐらいたっても治らないので、意を決して耳鼻科へ行くことに。半魚人におののいたにもかかわらず、外は雪世界なので、近くが良いということで、再びそこへ行った。
まずは受付で。
受付;以前いらした事はありますか?
私:はい、数年前に一度。
受付:(コンピューターをいろいろいじった結果)
あなたの名前は・・・・ないわ♪
私:(心の声)ないわ♪って・・・・・(-_-メ)
私:いえ、あの間違いなく来たのですが。
受付:新たな患者さんとして、もう一度手続きね♪ (←私が今、言った事は無視っすか・・。)
というわけで、私の半魚人との3年前の診察は、コンピュータ上には存在していないらしい。(謎1)
待合室で待つ事10分、診察室へ呼ばれた。
そして、握手を求めてきたお医者さんは・・・なんと!インターネットで見ていた
ドイツ人♪半魚人ではない!!!しかも診察室の隅には、秘書というか助手というか、若い女性がデスクに座っている。
私(心の声):半魚人には、助手いなかったけどなぁ・・・。(謎2)。
にこやかにあいさつしつつも、私は病院が苦手だ。やたら緊張する。右手と右足が一緒に出そうである。そんな中、奥へすすみ目の前にある椅子に、緊張しながら座ると、
医:あ、それ僕が座る椅子ね。向こうのいすに座ってね (・o・)
確かに、落ち着いてみれば、今私が座ろうとした椅子は、どうみても先生用である。
今のミスは、か・な・り・・・。
(* v v)。 ハズカシイ
=======
そして、問診が始まった。いつごろから痛くなったの? 熱や風邪の症状は???などなど・・・。そして
医者:何か家で薬は使いましたか?
私:はい、日本のトローチという薬と、それからスプレーをのどに・・
医者:スプレーって何の効果のスプレー?
私:( ゜o゜)ハッ 何って・・・えぇと、主人から勧められたので、何だったか・・えーと、えーと・・・(;^_^A アセアセ・・・汗)
医者:いやぁ、別にいいんだけどね。
そんなに大事なことじゃないから。(^-^)
私:コケッ! ミ(ノ;_ _)ノ =3
心の声:(じゃあ、聞くな!・・みたいな・・・。)
そして診察開始。のどを見せるため口をあける。
医者:これから棒を入れるから、声を出してこういう風に言っ・・・・・・
ここで私は、
あ、これは日本と同じ、のどの奥を見やす
いように“あー”っていうのね。(・o・)
と察し、
私:先生の文章が終わる前に、<あーーーーー>と先取り♪
ところが何と医者の出した声は………………….
ヒェーーーー♪
(゜∇゜ ;)エッ!?
ヒェーですよ、しかも先生のする例は、かなりひょろひょろの、か細い“裏声”のような音である。
おかげで私は、先取りしてはじめてしまった<あーーーー>から修正し、
私:(* ̄○ ̄)アアーーーーー(* ̄о ̄)ヒェーーーー・・・・・・
と何とも情けない声を出すことになったのである。
こんな医者初めてだ。
それにしても、半魚人はいずこへ・・・・そして私との診療記録はいずこへ・・・。はたまた、 ヒェーーーと言えなんて・・・。
なんともなぞな耳鼻科である。
私のサイトFromBerlinへは
こちらからhttp://www.rikakomurata.com
知らぬが仏?!
顔は3人ともアジア、でも国籍は日、中、韓。外国に住んでいるからこそあるのかもしれない、そういうメンバーで先日とある中華料理に行った。メンバーに中国人がいる以上、彼にメニュー選びを仕切ってもらおうと言う話に。
彼は私たち二人に、何か好きじゃないものはある?と親切にも気を使って質問してくれた。少し考えている私たちに、
中:辛いものは大丈夫?
というので、真っ先に韓国人の子が、
韓:私、韓国人よ!私にそんな事聞くなんて!笑
と、ひと蹴り。確かにそうだ。(・o・)
更に、
中:ニンニクとかは?
との質問に
韓:(-_-メ) だから、韓国人だってば。
中:あ、そうだった。(^-^)
と大笑い。でもその彼女は、おそるおそる、できればコリアンダーなんかの香料の強いのはちょっと苦手なので避けてほしいかも・・。というので、ここぞと私も便乗し、私もそれは少し苦手・・・と付け加えておいた。
中:羊の肉とかは?
私:あ、それは私苦手!
こんな感じのわがままにも中国君は笑顔でメニューを探し、彼の一存で注文してくれた。
人に注文してもらうと言うのは、何が出てくるのか分からない楽しみもある。
そして、最初になにやら前菜が運ばれてきた。
いっただっきまーす!
と早速、口にしてみると、強いニンニクの味と共に、なんだか少しこりっとするようなやわらかいような不思議な感触。味はとってもおいしい。
韓:おいしいね。これなぁに? ニンニク?
中:おいしいでしょう!これ?これは肺だよ♪ (^-^)
と、何とも涼しい顔。
今、なんていいました???(゜゜)
中:肺♪
韓:(/||| ̄▽)/ゲッ!!!
私(心の声):は・・・肺??肺っすか?
今、肺って言いました、あーた? ・・・みたいな。 (;^_^A アセアセ・・・
韓国彼女は、おいしい!と言っていたのにもかかわらず、
そこからそれには手をつけなかったような。笑
さすが中国君。頼むものがすごい。
しかし、それにしても辛いものは、ニンニクは?と質問するよりは
内臓は?と質問した方が良かったのでは・・。(-_-)
でもおかげさまで、普段食べないようなものをたくさん食べることができ大満足。しかもどれもこれもとってもおいしかった!
韓国彼女にとっては、知らぬがほとけ・・だったかな。
私のサイトFromBerlinへは
こちらからhttp://www.rikakomurata.com
仕方ない?
仕方ない?
日本語特訓中のDに、このあいだ
仕方ない
という言いまわしを教えてみた。
彼の頭の中では当然、漢字ではなく
SHI-KA-TA-NA-I
と覚えるので、どうも発音しにくいらしい。
いくらがんばっても
D:シタカナイ
となってしまう。(-_-メ)
D:シタカナイ シタカ? シカ?えーっと、シ・タ・カ・・・(・o・)
私:違うぅぅ。だから、し“か”た、だってばぁ。(-_-)
という問答を繰り返した末、
私:リカコ と同じように、 シカタ とおぼえて。
二つ目は<タ>じゃなくて<カ>なの!
と言ってみた。すると、
D:ほう!(゜-゜) りかこ・・・しかた・・なるほどねえ!
と納得がいったらしい。でも、それからこう練習し始めてしまった。
D:
りかこ しかたない
りかこ しかたない
りかこ 仕方ない・・・
Rikako Sikatanai!
どう考えてもいやな響きである。
私;あの・・・その練習方法やめてもらえませんか。(・・;)
こんな毎日を過ごしております。
私のサイト,FromBerlinへは
こちらからhttp://www.rikakomurata.com